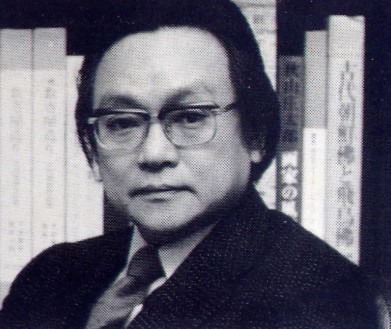| おすすめの古書紹介 | ||||
| 「兵庫商社」を創った最後の幕臣 | ||||
| 小栗上野介の生涯 | ||||
| 昭和62年9月10日 第1刷発行 講談社〈絶版本〉 | ||||
|
|
||||
| ●本書は、わたしの、文字どおりのライフ・ワークである。最初に小栗にとりくんでから、かれこれ30年になるのではなかろうか。資料はあつまり、構想は練られたけれど、なかなか一冊の本にはならず、今日になってしまった。 本書の約三分の二は、わたしの元気な間に執筆された。残りの三分の一は、肺ガンを病んで、痛みと苦しみのなかで、執筆された。東京女子医大病院中央病棟11階で、深夜ウンウンうなりながら、書きすすめられた。生きているうちに、何とか完成させたい、と思ったからである。途中、淋巴節その他への転移があり、絶望的ななかで、筆をすすめたこともある。 もっと突込んで研究したい個所も何個所かある。会って話をききたかった人、資料を探しに旅行したかった場所など、結局、あきらめないわけにはいかなかった。また、理論面でも、たとえば、兵庫商社が日本最初の株式会社であゐことの立証などについては、さらに深く考えたいが、それをやれば、まだ2年や3年はかかるだろう。それまで生きているという保証はない。 (著者の執筆メモより) |
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
| 小栗上野介の生涯 目次 | ||||
| プロローグ 幻の楽譜 | ||||
| 幻の楽譜/オグロ・ブソゴ・ノカミ/アメリカ人技師のショック 金と銀Iーなぜ日本の小判が大量に海外に流出したか メキシコの通貨を正式の政府通貨として承認した男の決断 日本人がアメリカ人の教師となる日/英国女王もおよばぬ歓迎ぶり 忘れられた小栗の偉業 |
||||
| 〈PARTI〉 | ||||
| 誕生 | ||||
| 「異国船無二念打払令(むにねんうちはらいれい)」とともに | ||||
| 世界が一大転換をとげたとぎ/なぜスペインは没落したのか 商社の源流/マンハッタン島を24ドルの品物と交換した男 イギリス、オランダを駆逐す “自由の女神〃がニューヨーク港に建っている事情” 世界に残された処女地、ニッポン/家斉の治世50年/イギリス船来航 シーボルト事件 |
||||
| 生まれた家 | ||||
| ―――――――― 家系、そして神田界隈 | ||||
| 遠 祖/「又一」命名由来/旗本としての小栗家 生家の位置/神田川の清流/忠順と築地小劇場 |
||||
| 少年時代 | ||||
| ―――――――― 塾生活と剣術修行 | ||||
| あばた/安精良斎の塾/心友、栗本鋤雲 直心影流−妙境に達した忠順の剣/剣のライバル、勝麟太郎 変則剣法・小栗流と龍馬/ひとつのエピソード/アヘン戦争、天保の改革 |
||||
| 就 職 | ||||
| 初登城―黒船前夜/二五歳の若き“首相”のもとで 就 職/世界史の転換−太平洋の時代へ 日本とアメリカの新しい関係−黒船来航 |
||||
| 結 婚 | ||||
| ―――――――― 小栗自身がつけた家計簿 | ||||
| 結婚、そして『家計簿』/側 室/ペリー来航 先輩幕臣たちの群像/ペリー来航、父の死、そして家計簿 神田祭の見物座席料に約五万円 |
||||
| 黒船と幕末政争 | ||||
| ―――――――― 小柴の先輩官僚の群像と論争 | ||||
| ロシアで出版直後に日本で邦訳された本/日本対ロシア、国境交渉史抄 日米和親条約/幕末政争の対立点/ハリス対岩瀬忠震 四面楚歌/井伊原弼の変貌/“安政の大獄”への前奏曲 |
||||
| 〈PART2〉 | ||||
| 訪 米 | ||||
| ―――――――― ライバル勝海舟 | ||||
| 使節任命/国書−むつびのちぎりのふみ/秘められた使命感 護衛艦と勝海舟/ハワイー新聞社訪問 サンフラソシスコでの再会−咸臨大の“神話”/旗印事件と祝砲事件 通貨交渉前哨戦−−j造幣局視察/日の丸の“幕”荒野を走る |
||||
| オグロ・ブソゴ | ||||
| ――――――――アメリカの新聞に載った日本人評 | ||||
| 国書奉呈式のリハーサル/アメリカ側の見た儀式 存在しない日付の「批准書」/勝海舟との混同/日本人の外観評、人間評 オグロ・ブンゴ・ノカミ評/従者トミー |
||||
| 帰 国 | ||||
| 幕末のアメリカ土産/j英国巨犬軍艦/風とともに去りぬ 小栗の独白/小栗の従者の記録/船中建白書 異様な雰囲気/さらばアメリカ/帰ってきた小栗 |
||||
| 露艦侵犯 | ||||
| ―――――――― ロシア水兵、対馬に不法上陸 | ||||
| 将軍を殺しても外国人を殺すな―安藤信正の時代 外国奉行・堀織部正の自殺/小栗の外国奉行就任とヒュースケン事件 ロシア軍艦の対馬侵犯/ロシアの意図 ―太平洋/島民の抵抗、逃げ腰の領主 |
||||
| 挫 折 | ||||
| ―――――――― 生命をかけた対露談判の失敗 | ||||
| 生命をかけた小栗の談判/安藤、勝の巧妙さ―毒を以て毒を制す 小栗忠順の挫折/因縁の島、対馬 |
||||
| 無役の日々 | ||||
| ―――――――― 対長州関係の転換 | ||||
| 鳥のまさに死なんとするや/幕政刷新/幕府の組織 ふたたび無役/長州軍の敗走/幕府内部の力関係の変化 歴史の皮肉 |
||||
| 洋式造船事始 | ||||
| 三本マストの洋式大型船−若き日の小栗の夢/ふたりの蘭学者の悲劇 「技術模倣は神国日本の特技」/日本最初の万国旗図集/ジョン万、江戸へ 象をつなぐ女性の髪の毛/密命―変装して黒船に乗りこむ 利用されたロシア艦 |
||||
| 土蔵つき売家 | ||||
| ―――――――― 日本の未来を考えた小栗の先見性 | ||||
| オランダ造船技師との一問一答/栗瀬兵衛と翔鶴丸/小栗と栗本の出会い ドック建造の夢/フラソスヘの傾斜/ロ″シュの底意 土蔵つなの売家/ヨコスカの選択 |
||||
| 横須賀製鉄所 | ||||
| ―――――――― アジアにおける近代的工業の夜明け | ||||
| 横須賀製鉄所建設計画の大綱/東洋一の大工場/小栗免職 フランス兵とイギリス兵/日本初の近代的語学“専門学校” 復 職/芝田日向守一行、パリヘ/ヴェルニーに二度驚く パリの日本人/イギリスの妨害/肥田浜五郎の反対論 横須賀のフランス人/横須賀製鉄所の建設費用 |
||||
| 近代的マネジメソトの導入 | ||||
| 近代的マネジメント トップ・マネジメント機構の革新−交替制から責任権限の一元化へ 組織および職務分掌/命令系統/部長織 頭目(監督者)の役割/混用関係細則/日本最初の奨励給 熟練工の採用と残業手当/“社内教育”事始に−日本人の独力運営へ日仏協力 洋式簿記の導入/森林保護育成の意見書 流通機構の近代化―姦商の独占利潤の排除 |
||||
| 〈PART3〉 | ||||
| 第二次征長と日仏組合商法 | ||||
| 小栗の征長論/第一次征長の結末/第二次征長と兵庫開港問題 小栗、海舟に極秘情報を打明ける/外国商人の貿易利益独占 国益会所の構想/商社組織の伺書/国土を担保にしたか |
||||
| 紙幣発行と三野村利左衛門 | ||||
| 無学文盲の大男/三井組と幕府の御用金/一石四鳥の名アイデア 三井組の実力人事/〈江戸銀座札‐日本の兌換紙幣のはじまり 朝廷・薩長側からの誘い/現体制は強力に見える/小栗への裏切り |
||||
| 兵庫商社 | ||||
| ―――――――― 日本最初の株式会社 | ||||
| インフレと庶民の困窮/小栗の諸構想の集大成/兵庫商社設立の建議書 コンペニー設立の出資手続/役員構成/武士、町人、百姓、誰でも出資を 役員の追加 |
||||
| 江戸開城 | ||||
| 新時代への胎動/坂本龍馬の平和革命路線/小栗上野介の“大統領”構想 慶喜の真意/西郷の武力革命路線/徳川家を丸裸にせよ 君側の奸、薩摩を討て/諸外国の[局外中立」宣言 |
||||
| 最後の幕臣 | ||||
| 烏川河原での非道の斬首 武士の美学/立往生した官軍/小栗の作戦計画 江戸か枚ったものは西郷、勝ではない/非道の斬首 無形の遺産 |
||||
| 兵庫商社・その後 | ||||
| ―――――――― 三井銀行、三井物産の源流 | ||||
| 東京貿易商社―‐兵庫商社の再現/通商会社、為替会社‐兵庫商社の継承 銀行設立の悲願/第一国立銀行の誕生/小野組の倒産 三井銀行、三井物産の創設/明治の三ケチ 日本最初の株式会社―その本質/現代の株式会社は有限責任か 兵庫商社の意義 |
||||
 |
||||
|
|
||||
| 地域づくり団体源流 sign104(古物商 群馬421030364600号)では 上記図書を全国よりを購入して『小栗まつり』昼市等で販売しております。 古書店・ネット等でご購入になれない場合は下記へご相談下さい。 |
||||
|